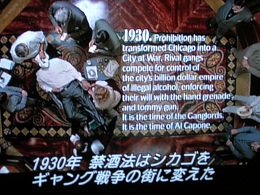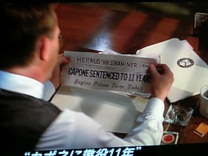「アンタッチャブル」(1987)を再見した。記事は数回目(笑)。
映画は、若き財務官エリオット・ネスが、ギャングの帝王、アル・カポネの時代に終止符を打つまでの様子をコンパクトにまとめている。テレビの「アンタッチャブル」は、シリーズで、毎週ドラマを見ていたが、サスペンスの名手、ブライアン・デ・パルマが、冴える。

ネス(ケヴィン・コスナー)は、一人でアル・カポネに立ち向かうことは困難と見て、たまたま帰宅途中で出あった巡回中の巡査、マローン(ショーン・コネリー:アカデミー賞助演男優賞)の一言一言に感銘を受け、協力を依頼する。
マローンは、ネスにとって、師匠のような存在となる。マローンは、優秀そうな警官を引き抜く。
警官の心得も伝授する。
「心得の第一は、毎日生きて家へ帰る」だった(笑)。当たり前のことだが、職業的な厳しさをついている。
「無料講習をしろっていうのか」
「きょうの講習は終わり!」
という一言も、ユーモアがあっていい。
映画のラストで、ネスは、この”師匠”のことばをそっくり使っていた。
後に「心得の第二は、上司に秘密の情報を伝えるな」だった。
実際に、このカポネの時代、警察の幹部がこぞって、カポネに買収されているという腐った組織だった。
映画は冒頭から、ぞくぞくするような音楽が響く。
「アンタッチャブル」の文字に影のシルエットがつき、出だしから期待させる。
画面に文字が流れる。
「1930年代はギャングの時代だった。」
「アル・カポネの時代だった。」
劇中、アル・カポネ(ロバート・デ・ニーロ)はすごむ。
「俺の育ったところでは、人々は、優しい言葉よりも、拳銃の言うことを聞く。」
新聞記者が、カポネの威光をおそれて、提灯記事を書く。
記者団を前にして、さらに、いう。「決闘は、最後まで見ろ。(最後に)立っている方が
勝ちだ。」
それにしても、エンニオ・モリコ―ネの音楽。
デ・パルマのカメラ。カメラが人の目のように、動く。
乳母車。計算しつくされた演出。
実は一度目の観賞は、米国(字幕なし)だったので、再観賞が必要だったが、CS放送・大画面で再見することができたのでした(爆)。
以前の紹介記事:
☆☆☆☆
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:
ついでにクリック・ポン♪。